学校法人三幸学園の運営する、保育士と幼稚園教諭の資格が取得できる課程で、資格に関わる重要科目となる単位認定試験で、「学習の手引き」を持ち込み可としていたことがわかりました。報道によれば、発覚したのは「札幌こども専門学校」で、この「学習の手引き」は教科書であると共に、試験問題の模範解答集でもあるから、想定された問題が出題によっては、書き写すだけで容易に満点が取れるいうものでした。
同法人が運営する同種の専門学校は以下の通りです。各専門学校の生徒は教育連携制度として通信制の短期大学である小田原短期大学に在学することで、専門学校卒の称号となる「専門士」と、短大卒の学位となる「短期大学士」が同時に取得できるというメリットがあります。

三幸学園が運営する保育士・幼稚園教諭養成の専門学校一覧
- 札幌こども専門学校
- 仙台こども専門学校
- 東京立川こども専門学校
- 大宮こども専門学校
- 千葉こども専門学校
- 東京こども専門学校
- 横浜こども専門学校
- 名古屋こども専門学校
- 大阪こども専門学校
- 神戸元町こども専門学校
- 福岡こども専門学校
- 沖縄こども専門学校
上記各こども専門学校のホームページによれば、小田原短期大学の説明を読むよう指示されていました。以下の通りです。
本学通信教育課程に関する報道について(6月30日) – 小田原短期大学 保育学科 通信教育課程
本学通信課程の科目修得試験に関する報道がございましたが、6月19日付の「本学通信教育課程に関する報道について」の通り、成績・評価・単位付与に影響を及ぼすものではないことを確認しております。
【お知らせ(2025年6月19日付)】https://tsushin.odawara.ac.jp/news/20250619-1211/
本課程による学びにおいては、学生はテキスト履修(印刷教材授業)、スクーリング履修(面接授業)、教育実習において、添削・指導を受けながら学習の過程を経て学び、単位を修得し、卒業および資格・免許を取得しております。
今回の報道では、本課程のテキスト履修(印刷教材授業)の科目修得試験が指摘されておりますが、本課程の科目修得試験が丸写しにより、ほとんどの学生が100点満点という事実はございません。
このテキスト履修は、学生自身が「学習の手引き」に沿った形で教科書を学習する中で学習時間を担保し、授業科目の内容の理解を促し、学習を積み重ね、中間試験(「到達基準」に名称変更)の到達基準を達成することにより、はじめて科目修得試験の受験が可能になります。
この科目修得試験において、「学習の手引き」の出題の一部(2024年度において16%)と同じ内容での出題があったことが指摘されています。
この科目修得試験の試験結果として、2024年度の科目修得試験において100点満点であった学生の人数は全体の7.42%です。
従いまして、科目修得試験においては、100点満点はそうそう取れるものではありません。また、中間試験(到達基準)を達成しない学生は、科目修得試験を受験することができない仕組みになっています。
学生が、何も学習の過程を経ずに模範解答を見ながら試験を受けて単位を修得できるという報道内容については、本学の学習の仕組みからはあり得ません。学生は卒業、免許取得、資格取得に向けて、相当の学修時間を経ております。
なお、2020年度から2022年度まではコロナ禍による対応のため、当初は試験会場でのペーパー試験のみで実施していましたが、対面による実施の制限があったことにより、やむを得ずオンラインでの試験を導入し、それぞれ公平性を鑑み持ち込み可能とする対応をしておりました。2023年度の新型コロナウイルスの5類感染症移行後も通信教育の学習方法やICT教育への期待の高まりを鑑み、オンラインでの試験を継続しており、実施方法は改善済みです。
・学習の手引き
学習の手引きは、自宅で学習を進めるため本学教員が作成したオリジナル学習教材補助教材のことで、テキスト履修における学習ポイントや課題がまとめられています。学習目標や学習方法・達成課題などが掲載されており、その教科書のどの部分が重要で、どこを学習してほしいかがわかるようになっていて、2単位分の授業科目は15講に区分され、各講の内容がしっかり身についているかをチェックするための「理解度テスト」と「レポートテスト」により、学習の定着を図れるよう工夫されています。・中間試験(「到達基準」に名称変更)
テキスト履修における当該授業科目の科目修得試験の受験資格を得るための到達基準であります。学生は、「学習の手引き」の解答欄に記入して、科目修得試験前の指定期日までに提出します。60点以上を到達基準とし、その解答には添削指導が行われます。学生は、これを繰り返し学習し、再提出することが可能です。・科目修得試験
「科目修得試験」は、短期大学通信教育設置基準における「印刷教材等による授業」の一部であり、本学学則に基づく通信教育課程試験規程で定義している「テキスト履修」のプロセスです。・テキスト履修
学生は「教科書、学習の手引きによる自主学習」をし「中間試験(学習の手引きの実施)」 の基準に到達すれば「科目修得試験」を受験でき、その試験に合格すれば単位修得となる授業です。本件にかかるお問い合わせ 小田原短期大学事務局 経営企画室 info●省略●.ac.jp
この説明を簡単に説明すれば、以下のようになると思います。
1.2020~22年度についてはコロナ禍の経過措置であったこと
2.「学習の手引き」は完全な模範解答集ではなくて、16%程度の一致であったこと
3.満点が続出していたというが、実態は7.4%程度だったということ
1.コロナ禍の経過措置
学校側の立場からすれは、確かに2020~22年のコロナ禍は、教育業界では空前の改革がなされた、てんやわんやの過渡期となりました。そもそも教室や試験会場は過密となりがちで、発熱などの体調不良の学生だけでなく、濃厚接触者には登校を控えさせるなど、試験そのものを開催することが困難でした。致し方なく、合格基準点を下げる、分散開催、追試・再試などの対応に迫られた学校も多くあります。
例えば、放送大学では、学生の多くが高齢者だったこともあり、本来は試験会場で配布・受験するはずの試験問題を学生の自宅に送り、自宅で解答・郵送で提出としたこともあります。つまり、本来の1時間の時間制限もなければ、持ち込み不可とされている科目でも、試験監督がいなのだから、満点が続出した時期でもありました。こんな事情もあって、コロナ禍については学校側の試行錯誤もあったし、合格点を下げてでも卒業させるべきと判断したのも致し方ありません。
2.持ち込み可能科目の可否
全国で通用する教員免許の単位認定試験の難易度を、学校側の独断で決めていいのかという議論は確かにあります。
例えば大学の医学部は、卒業がそのまま医師免許となる訳ではなく、医師国家試験の受験資格が得られるだけで、別に全国統一の試験を受けなければなりません。
しかし、教員免許は、いわば大学等で所定の教職課程を修了すればよく、所定の単位を修得できさえすればいいので、大学の運営方針によって、いくらでも難易度を調節することができます。
また、通信制大学には「卒業率○%」などと、卒業しやすさを売りにしているところもあります。これについては、「うちはめっちゃ簡単に大卒になれます(難易度めっちゃ低いよ)」という広告宣伝と同じといえます。
より難易度を高くする、または低くするのは大学の裁量と考えれば、教科書持ち込みを可とした学校の判断は、不正とまではいえません。
3.満点続出は大半なのか一部だったのか
これについては個別の話で、報道か小田原短大の説明から推測するしかできません。おそらく、どちらも正しいのかもしれません。満点が続出したケースもあったし、そうでもないケースもあったのではないかと思います。
これについては、詳細に調べないとわかりませんが、詳細に調べたところで、「この科目はたまたま合格基準が甘かった」という程度の結果しか出ないと思います。
高等教育を経験した人なら理解できると思いますが、「この先生は出席だけで単位をくれる」とか、「この科目は出席はカウントせずに試験だけで単位が取れる」といった、攻略法みたいなものが存在したはずです。全ての科目に全力を投じて卒業する人など、極めて少ないのではないでしょうか。
試験問題が難解であれば良き教師になれるのか
三幸学園の専門学校や小田原短期大学を批判する報道で、元教員の男性の証言で、卒業生を採用した現場の幼稚園から「担任を任せたけれど、一切仕事ができない」「この人本当に免許を取ったんですか」という能力不足を問う質問がなされたとあります。
この指摘は大切ですが、例えば100人の卒業生を追跡調査したとして、15人は優秀、70人は人並み、残り15人は能力不足という結果が出たとします。この数値は、「標準分布」と呼ばれる偏差値のようなもので、世の中のあらゆるものを計測した時に現れる基本的な分布傾向として有名ですが、能力が低いというクレームは、まさにこの「能力不足の15人」についてだったのではないかと想像できます。
しかし、教育や調査を行う人なら、能力や得点は「標準分布」で分かれることを知っています。運転免許を持っている人を100人集めたら、そのうち下位15人程度は事故やうっかりミス予備軍だし、難解な試験問題を突破した優秀な若者を100人雇い入れても、やはり下位15人程度は使い物にならないというのはよくあることです。プロ野球NPB12球団は、同時に1チーム70人までを支配下に置くことができますが、一軍でプレーできるのはそのうち30人程度で、しかもグラウンドに立てるのは9人と考えれば、まさに正規分布通り。プロとして活躍できる9人がいるということは、それに相対する使えない9人が存在するのです。
三幸学園はどうすべきだったのか
前述した通り、三幸学園は専門学校と、通信制の短期大学を有しています。これらを組み合わせることで、保育士と幼稚園教諭の免許を同時に取得できるカリキュラムを持ち、専門学校卒の称号とされる「専門士」と、短大卒として評価される「短期大学士」を取得できます。
学校が目指すべきは、卒業生全員が成績優秀で、持ち込みせずとも小論文試をパスできる読解力・文章力を有し、かつ幼児の健全な最長をサポートできる教育のエキスパートであります。しかし、それは先ほど示した通り単なる理想でしかありません。これは三幸学園側が言うと炎上してしまうでしょうから、私が言います。
1.専門学校を卒業しただけの人の能力はたかが知れている
例えば運転免許。自動車学校を卒業して免許証を手にした人が、いきなり都内の首都高速道路に乗るとか、狭い駐車場に駐車するって、けっこう大変ですよね。それと同じように、専門学校で専門的なことを学んだといっても、プロとして要求されるレベルの実務に達するには時間がかかります。
まして、幼稚園とはいえ、教職でしょう?慣れていない教諭がいろんな性格の子どもたちを扱うって、どれだけ難しいか。そもそも新卒にプロとしての力量を求めるのは無理な話です。仮に採用2~3年の幼稚園教諭について、「この教員、使えないなぁ」という人物がいたとしてもそれは普通で、使えない教員を採用してしまったことについて、出身校に電話で苦情を伝えるというのは愚の骨頂でしかありません。これについては幼稚園・保育園のマネジメントの怠慢だと思います。
また、仕事の現場は全て同じではありません。現場単位でルールも違えば、登園する児童の性格も違います。地方・地域の特性も様々です。どんなこどもでも、どんな環境でも、どんなモンスターペアレンツでもコントロールできて、同僚とも仲良くできるなんてエキスパートなんて、そうそういません。専門学校が保証できるのは、せいぜいその現場で勤務できる免許・資格を取得させていることです。
2.文部科学省の指導に従いつつも、生徒に寄り添う
一般的に、文系の専門学校は、入試の際に学力試験を行いません。つまり、高校卒業時の成績や面接で合否を決めます。必要に応じて簡単なテストをいますが、その程度です。定員充足率が足りなければ、形式だけとする学校もあるでしょう。
三幸学園は、専門学校と通信制大学を合わせて在学することで、幼稚園教諭や保育士の免許を取得させるための最小限の教育課程を持っているに過ぎません。
一般の大学などでも「教科書持ち込み可」の試験があるように、今回のようなルールで試験を行うことは、不正ではありません。学校や教員の判断で「これでいい」と考えれば、それで良しとできるのです。もちろん、持ち込み可能といいながら、実はほぼ模範解答となっていて良いわけではありません。つまり、一定のハードルは設けつつも、学校・教員の判断で単位を与えても良いのです。それを軽々しく学校ぐるみでカンニングみたいな報じ方はよくありません。
三幸学園は文科省から指導された以上、対応しない訳にもいきません。改革に向かうことになります。ただし、それが露骨に難易度を上げることであるなら、それはそれで卒業にかかわる生徒は負担になるし、そのような生徒へのサポートも大変です。
難易度を上げつつ、落単しないような指導という、難しめの試行錯誤が必要となります。
懲戒解雇された教員の扱いはどうすべきか
今回、公益通報したとされる教員が懲戒解雇されてしまったというのは残念です。
専門学校としての学校の質を保ちたいと思っているのに、容易に試験で満点を取れてしまうようなカリキュラムに疑問を持つのは、まじめな教員であれば当然です。
教員の理想は理解しつつも、学校側としては、卒業や資格に必要な単位の合格認定について、不用意に難易度を上げるのも難しい。
当初、「学校ぐるみのカンニング」と報じられていたので、違法なイメージがありますが、教材の持ち込みを許したことは違法ではありません。「公益通報」という捉え方もできなくはないのですが、それも行き過ぎ。違法ではないといっても、教育者を養成する課程で、あまりにも楽勝な単位認定基準はいかがなものかというモラルの問題は残ります。
私は思い切り外部の人間なので、詳細はわかりかねますが、ここは公益通報に準ずる重要な指摘として捉え、懲戒解雇はいったん取り消した上で話し合いが持たれるべきかと思います。
ちなみに私も専門学校の非常勤講師をしています。単位認定の判断する権限は私にあり、しかも必修ですから、私の単位が取れていない場合は卒業できないことになっています。私の授業は出席日数と期末試験の結果で判断しますが、補習や追試などで、可能な限り生徒の事情に寄り添うことにしています。
結論
今回の事件ですが、あくまで報道をベースにした私の意見です。
1.コロナ禍における試験開催や単位認定にかかる混乱が発端だった
2.報道された教材持ち込みの試験は、不正行為とまではいえない
3.容易に単位が取れる試験は、文科省が疑義を抱く不適切な試験方法であった
4.試験の難易度を上げたところで、能力の乏しい人材は必ず生まれてしまう
5.指摘した教員に対する懲戒解雇処分は行き過ぎの可能性がある
6.三幸学園は早期に適切な試験を執り行うべき
最後に一言。
三幸学園の幼稚園教諭(二種)と保育士資格が2年間で取れてしまうこのカリキュラムは、実はとても興味深いと思います。地元の専門学校で資格が取れて、通信制短大のサポートも受けられるというのはとても良い。しかも系列校には東京未来大学もあり、学士や小学校教諭の資格にも手が届きます。
このような合理的なカリキュラムを持っている専門学校・短大・大学グループというのは貴重だと思いますので、応援していきたいと思います。
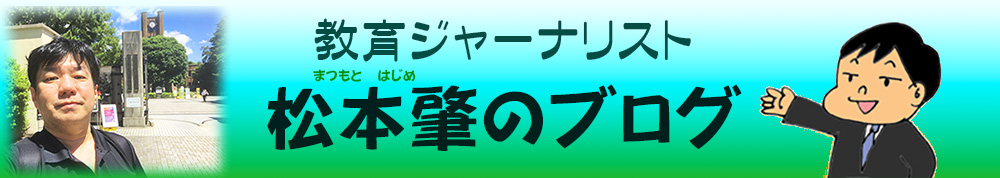


コメント