著作権法重要判例のひとつとなっている「スメルゲット事件」ですが、この訴訟の原告は私であります。弁護士をつけずに行った、いわゆる本人訴訟です。
私がネットショップを行うに当たって撮影したこちらの商品画像を他社が違法にコピペして、自社のショッピングサイトに掲載したことが著作権法侵害であるとして提訴。

しかし、なんと一審の横浜地裁は私の100%敗訴。私が撮影した画像を、他人が無断で使用して、訴訟して私が負けるって何それ?
あまりにも理不尽な一審判決が悔しくて控訴。私が作成した控訴理由書は、大した内容でもないのに、簡単にひっくり返り、逆転勝訴となったのでした。
できて間もない知的財産高等裁判所、略して「知財高裁」ですが、実はそんな裁判所ができたことを知らず、電話で書記官さんから電話をいただいた際、「チザイコウサイ」と言われ、「痴罪交際」と脳内変換してしまった私。一瞬、何かヤバい事件に巻き込まれてしまったかと。アホですね。
そんな私でも簡単に「逆転勝訴」ですぜ。逆に、一審の横浜地裁はアホだったと確信しました。裁判官の資質を疑いました。

この判決は最高裁判例集に掲載され、著作権法判例百選にも掲載されるリーディングケースになりました。「他人のホームページの画像を無断で使用してはいけない」というのは、今では子どもでも理解できるはずですが、この知財高裁判決が出るまで判例が無かったことから、法律家の間では「著作物とは思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものだから、素人が撮影した商品写真(商品をただ撮影しただけ)には思想も感情も無いから著作物ではない」という言説がまかり通っていたのです。
当時、私は日本の偉い先生方(弁護士・弁理士・警察)に本件の相談したところ、口を揃えて「松本は裁判では勝てない」と言っていました。現実に一審は負けたので彼らの言うことも妥当性はあったのでしょう。しかし、控訴したら素人の私の戯言でひっくり返った事件です。
たかがこんな画像の事件が最高裁判例集に載るなんて、考えられないでしょ?
ちなみに、スメルゲットというのは、こういう形状の消臭剤でして、ホムルアルデヒドを吸着して無害化する特性を持っていることから、シックハウス症候群対策に効く製品としてよく売れていました。
で、無断で使用されて問題となったのはまさにこれらの画像です。ウェブサイトの企画・撮影・制作まで、全て私がひとりで行いましたので、著作財産権を有するのは私の会社「トライアル」で、著作者人格権を有するのは撮影した私こと松本肇です。ただ、もうこの商品は存在しないし、販売もしておりませんので、学術的な目的であれば、私の許諾無しに、どうぞご自由にお使いください。
とはいえ、一般的な方法による引用元の記載を願います。「撮影:松本肇」とか「©松本肇」とでも書いていただければOKです。もし可能なら、事後報告でかまいませんので、どこに掲載したかなどを教えていただくとうれしいです。
スメルゲット画像



この著作権訴訟の顛末は本になっています。よろしければ、拙著 ホームページ泥棒をやっつける をお買い上げください。毎日新聞の書評にも採り上げられました。判例百選への初掲載は第4版です。
判決文はこちらにあります。判決文に出てくる「ラフィーネ」は当時私が取締役を務めていたネット通販会社、で「トライアル」は私が代表を務めていた制作会社です。
ちなみに、四半世紀前の拙いウェブサイトですが、こんな感じです。今となってはダサ過ぎですが、まぁ、それはご勘弁。

スメルゲット事件後の社会の変容
私は本件の原告だからわかることでもあるのですが、実は、世の中の著作権って、思いのほか守られていません。大手旅行代理店の関連会社が、旅行のパンフレットを作成するにあたり、各種画像・映像コンテンツを制作販売する会社の画像データを、無断で使用していたことが問題になりました。これはJTBという大手旅行代理店傘下の広告代理店従業員の書類送検という刑事事件にも発展しました。
奇遇ですが、実は私、この広告代理店から仕事を受けていたことがあります。私の担当となった社員が、これまた陰湿なパワハラ野郎で、暴行・暴言・接待要求などが頻繁にあったことから想像するに、下請け会社としては抗議しにくい関係があったことが伺えます。そりゃ刑事事件にもなるよね。
そしてスメルゲット事件後、商品画像であったとしても、たまたまシャッターを切っただけの無意識の画像であったとしても、それらは著作物として認められるという判決理由での判例となったため、警察も重い腰を上げたと聞いています。
その後、テレビ局が画像・映像を使う時、特に過去の画像・映像を再利用する場合は、撮影したカメラマンや関係者の許諾が必要というコンプライアンスが徹底されることになり、許諾の必要な相手が不明な時は、例えばタレントの画像をイラスト風に加工するなどの処理がなされるようになりました。
更に、映像コンテンツを収集して著作権者に還元されるようなシステムを有する画像・映像管理会社ができました。テレビなどで「©アフロ」などと表記されるようになったので、見覚えのある人も多いと思います。つまり、新たなビジネスが生まれることにつながったのです。
著作権と剽窃論文
私は神奈川大学大学院を修了し、修士(法学)を持っています。専門は民事訴訟法でした。この修士論文を作成するにあたり、他人の著作物はきちんと転載・引用を明らかにしなければならないと、指導教授に教え込まれました。当たり前といえば当たり前の話ですが、1990年代初頭、私が在籍してきた神奈川大学法学部は、今でいうところの「アカデミックスキル」とか「アカデミックライティング」の技術を学部で教わることはほとんどありませんでした。当時の法学部といえば、「いかに大学の授業を受けずに試験だけで単位を取れたか」が自慢になっていた時代でもあり、研究者としてのスキルは大学院でなければ学ぶことができなかったともいえます。
私は決して優秀な学生ではありませんでしたが、不思議なことに、文章を読むと、その文章を書いた人物の情景が映像化されるような不思議な感覚があります。そのせいか、剽窃・無断引用・転載論文を読むと、違和感をいだくのでした。超能力者とまでは言いませんが、何かこれが気持ち悪いのです。
後に、本を読んで著者を尊敬していたものの、実際にその著者と会談した時にものすごく違和感を得るという経験がありました。つまり、ゴーストライターか剽窃を疑ってしまうのです。そのような論文を作成してきた研究者には嫌われたり、嫌がらせを受けてきたこともあります。悲しいかな、そういう嫌がらせを行う研究者とされる人たちは、人が羨む学歴を持っている人が多いのですが、中身が伴っていません。私が「旧帝大卒」とか「MARCH」といったブランド大学信奉者を、虚飾と感じてしまうのは、外見よりも中身が重要という、自分なりの信条があるからかもしれません。
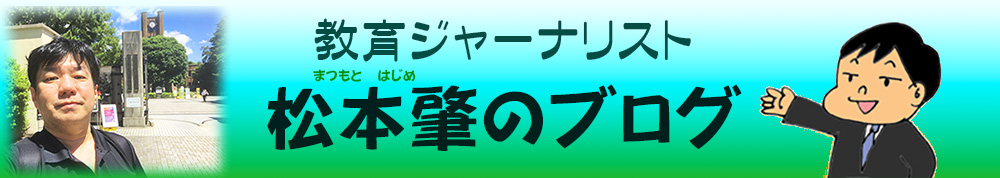


コメント